ブログ
ブログ一覧
ほんのわずかな期間、秋田にとてもいいインクルーシブ教育があった
ーー 1月28日 ーー
今から25年くらい前に秋田県の男鹿南秋(おがなんしゅう)地区に養護学校(今は特別支援学校と言う)を作ろうと住民運動がありました。私はその運動組織の中で願いが実現するようにがんばっていました。運動は順調に進んで目的は達成されました。新たな養護学校が開校するまでの間、経過措置として地域の小学校内に養護学校の分教室が設置されました。
地域の小さな小学校、その校舎内に県立の養護学校の分教室が設置される。これは、過渡的な措置であって、念願の養護学校が建築されればすぐになくなるものだとしても、画期的でした。「インクルーシブ教育は、多様な子どもたちがいることを前提とし、その多様な子どもたち(排除されやすい子どもたちを含む)の教育を受ける権利を地域の学校で保障するために、教育システムそのものを改革していくプロセス」(ユネスコのインクルージョンガイドライン)を実現するものだとわくわくしました。
実は、私はその小学校に勤務していたのですが、分教室ができるまさにその時に中学校に転勤になりました。だから、分教室があった期間の様子を直に感じていません。新たに養護学校が建設されて、分教室が消えて数年後、当時その小学校と分教室にそれぞれ勤務していた何人もの先生たちから、「とてもよかった」「理想的だった」と聞きました。「自然に交流していた」、「休み時間に小学校の子どもたちが分教室に遊びに来て、自然に声をかけあっていた」、「集会に参加した分教室の子どもが声を出すと、小学校の子どもたちが振り返ってその子どもを見ていた。やがて、声が出ても、誰も気にしなくなった」など。ある先生は私に「あの様子を記録としてまとめたらいい」と勧めてくれました。私にできるわけもなかったのですが、そう勧めてくれるほどの貴重な期間だったと思うのです。
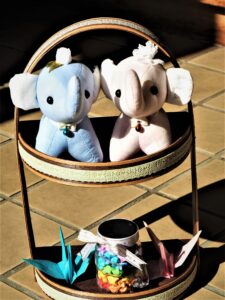
学習支援は子どもの様子を見てあれこれと試してみる 支援に労力を惜しまない
ーー 5月15日 ーー
「これ以上の勉強の支援は難しいのではないか」と先生は言うけれど、「どうにかして小学4年生の割り算まで習得できないだろうか」と希望を捨てきれないお母さん。またまた「それじゃあ、うちでやってみましょうか」と。
ということで、運動支援は妻に任せて、学習支援は私の直接支援に。
数詞は言うし、数字を読んで書ける。でも、たとえば、「3」と具体物3つが結びついていない感じがした。たとえば「ゾウが3頭とあめ玉3個を、同じ『3』で表象できていないのではないか?」とも感じた。
ところで、勉強は、ここで生きているAさんがするもので、Aさんが納得できるような内容で指導しなければならない。学校に楽しく行って同学年の子どもたちと過ごしている小学生のAさんに、基礎的な訓練のようなことを繰り返したって、つまらないのではないだろうか?
ということで、できるだけAさんの学年に近い学習内容で勉強開始。
「一桁+一桁=二桁」の繰り上がりの計算で、解いていく手順がわかりやすいように数式にヒントを記して指導してみた。少しの間一緒に解いていったら、Aさん一人でできるではないか!
これに味を占めて、繰り下がりを指導してみたが、うまくいかない。そうしたところ、繰り上がりができることを知った小学校が、今度は算数専門の先生が繰り下がりの指導をしてくれて、できるようになっちゃった。
ということで、算数の勉強が着実に進んでいっている。
国語もごく初歩的な読み取り問題をやってみたができない。Aさんにわかりやすいように、答えになる部分を含んでいる文章に傍線を引いて示して、そこから答えになる部分を取り出しやすいようにしたが、どうもすっきりしない。
そこで、市販の初歩的な問題集の1ページ分の問題文からさらにAさんが答えやすいように自作プリントを作ってみた。
たとえば、「くまさんが歩いて、りすさんのおうちに行って、それからうさぎさんのおうちに行きました」というような内容の文章に対して、問題が「誰が歩いて行きましたか?」だとします。これだとAさんは迷いの世界に入ってしまう。これに対して自作プリントで、「だれがでてきましたか?」と問い、解答欄に「とらさん くまさん うさぎさん Aさん りすさん」と記しておいて登場人物に〇をつけるようにします。Aさん、大喜びで正しく〇をつけます。問題文に自分の名前が出てきたり、なじみのスーパーマーケットの名前が出てきたりすると、大喜びでがぜんやる気が出ます。そのあとで、「誰が歩いて行きましたか?」の問いに即座に「くまさん」と答えます。 このことは、Aさんが全然理解していないということではないですよね。しかも、Aさん、笑い転げるようにしてこの学習に向かってくる。
これでいいのだろうか?いや、いいもわるいもないのではなかろうか?どんな人であれ、実際に生活している人が何も考えないということはありえない。Aさんのように素直でまっすぐで人が大好きなで、自分なりにいっしょうけんめい生きていこうとしている子どもに、みんながしている勉強についても支援をしていく。人それぞれに自分に合った思考とか記憶とか感じ方があるはずです。それに応じて支援していく。Aさんが支援者とかかわって積極的に学習をしている。支援する私も楽しく幸せだ。

これも理想的な運動支援
ーー 5月13日 ーー
相談事業所では、利用者さん一人ずつに通常は半年に一回モニタリングをします。お母さんが「運動も勉強ももっと指導してほしいんだけど」と話すので、「それじゃあ、うちの事業所でボランティアでやってみましょうか」ということに。
普通は相談事業所が子どもに直接支援をすることはありませんが、私は、「やってみればうまくいくのではないか」と思い、やりたいのでした。しかし、とても忙しくて現実には私にはできない。頭にあるのは妻のことで「きっとやってくれるべ」と期待して、子どものお母さんに「うちでやりましょう」。
子ども用のおもちゃのバット・グローブ・ボールを持って意気揚々とやってきます。子どもも妻も、実は野球のルールをくわしくは知らない。子どもがまっすぐな心をもっていて、自分が楽しくできると思うルールでさっさとゲーム開始。とにかく遊んで楽しみたい子どもと、何とかして運動機能の衰えを防ぎたい初老の妻が、ワイワイギャーギャーと戦い、いつも「5対3で、〇〇さんの勝ち!」などという調子で、〇〇さんは事務室にいる私に、「今日も◇◇さん(妻)が負けたよ」と報告に来るのです。
こんなことをしていると聞いたBさんが「息子がとにかく運動が苦手で」と電話をくれました。またまた妻の出番で、風船バレーボールなど、お母さんも妹さんも時にはお父さんも加わって「ソレー」「エイ!」と楽しみます。退職した前の担任の先生が駆けつけたことがありました。みんななかよく楽しみます。
これは私にとって理想的な姿です。

努力はうそをつかない
ーー 2月3日 ーー
昨年同じころにお師匠さんが初めて連れて行ってくれた場所です。
昨年のブログにも書きましたが、わずか2回滑って、体力の限界で心が折れた場所です。
「これではいけない」と思い、春からジョギングをして、今回はほぼ予定通り4回滑って登ってくるこができました。
お師匠さんから「努力はうそをつかないね」と言われて、安堵しました。
これからも体力増強とスキー技術向上に努力です。

ただいるだけで、人が人を助けることがあるのですね
ーー 1月23日 ーー
障害者の相談事業所の相談支援専門員である私が支援する人たちには障害がある。私の事業所と契約しているKさんは就労継続支援A型事業所を利用している。Kさんはあるがままの自分として生きている。ごく普通に仕事をして、この事業所の利用者さんたちから慕われている。ミスが少ないとか、素直であるとか、円満な人なのだが、それはKさんが特別ということではなく、一般的にこういう人はいるよね。
このA型事業所でKさんを特別に慕っている方がいる。精神障害があれば、生きていくことが特別につらいこともある。この方は一週間連続して休まずに勤務を続けることがなかなかできない状態が続いていた。そこにKさんが現れた。この方はKさんを慕って、いつも一緒にいたいと思い、それをKさんは受け入れて-Kさんは誰をも分け隔てなく受け入れる―この方の思いは達成されている。
予定していた勤務日の半分ぐらいも休んでいたこの方は、驚いたことに、ほぼ毎日出勤して働くようになった。事業所のスタッフは、どの利用者さんも働きやすいように配慮をしている。この方も、そのような環境で努力して働こうとしてきたが、それでも休まざるを得なかった。ところが、Kさんとおつきあいするようになって、毎日出勤するようになった。すごいことだと思う。
私がKさんにこのことをホームページに書いていいかと聞いたら、いつものごとく「ああ、はい」と、こころよい返事。「相手の方もいるから、その方もいいかな?」に「いいですよ」と軽い返事。
Kさんは自分でたいしたことをしているとは思っていないし、実際すごい努力をしているのでもない。けれども、すごく人にいい影響を与えている。これって、なんだろう?なんだかわからないが、実際にこういうことが起こっている。
Kさん自身、身体障害があって、加齢から痛みも出ている。本人のせいでもないのに軽くもない病気がやってくる。つらい体験を繰り返してきたようだ。自己評価も高くないようだ。でも、Kさんと話していると、ざらざらした感じがない。「どうして?」なんて考えたってわからない。実際にこういう人がいて、この方の周りの方々を具体的に何かをして助けるということでもなく、ただ一緒にいれば落ち着いて、とても助かっているという人たちがいるという事実。よくわからないのだが、神様仏様のような人だと私は思う。
